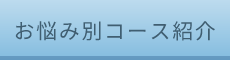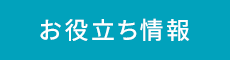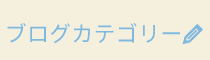くすぐったいその反応、エネルギー無駄遣いしてませんか?
「ちょっと触れただけなのに、くすぐったすぎて動けない!」
「マッサージを受けるとくすぐったくてリラックスできない…」
そんな経験、ありませんか?
実はこの「くすぐったい!」という反応、起立性調節障害(OD)の人にとっては、ただの感覚ではなく、体力やエネルギーをムダに浪費してしまうサインなのです。
今回は、くすぐったさと起立性調節障害の深~い関係、そしてなぜその反応が体に負担をかけるのか?どうすれば「くすぐった地獄」から抜け出せるのか?について、面白おかしく、でも真面目に解説していきます。
くすぐったさの正体って?
くすぐったさって、なんとなく笑っちゃう感覚…だけじゃないんです。
この感覚は、神経系の働きによって生じます。皮膚の表面には感覚受容器というセンサーがあり、そこが刺激を受けると脳に「何か触られた!」という信号が送られます。
本来であれば、
「気持ちいい」
「優しく触れられた」
といった感覚で済むはずが…
自律神経が乱れている状態では、その信号を“危険信号”として処理してしまうことがあるのです。
つまり、普通の人ならリラックスするはずの刺激を、ODの人は**「うわ!くすぐったい!やめてー!」と全身で警戒**してしまうんですね。
なぜくすぐったさがエネルギーを奪うのか?
ここが今回のキモです。
結論から言うと、くすぐったさは“体力のムダ遣いスイッチ”を押してしまうんです。
どういうことかというと、
-
軽く触れられる
↓ -
神経が「敵襲だ!」と過剰反応
↓ -
交感神経(=戦うモード)がオン!
↓ -
心拍数アップ、筋肉ガチガチ、体中が緊張
↓ -
そのままどっと疲れる
…という流れ。
まるで、くすぐったさ=「一瞬で戦闘モードに突入して全エネルギーを放出するスイッチ」。
しかもこれ、毎日のように繰り返されると本当にしんどい。
学校に行く準備をしてる途中で誰かに背中をポンとされて「くすぐったい〜!」と暴れた結果、すでに朝からエネルギー0。
これじゃ登校どころじゃないですよね。
起立性調節障害と感覚過敏の関係
そもそも、なぜODの人はこんなにもくすぐったさに敏感なのでしょうか?
それは、自律神経の乱れにより「感覚神経」が過敏になっているから。
-
血流の悪さで神経が栄養不足に陥りやすい
-
交感神経の緊張が続いて神経が常にピリピリしている
-
睡眠の質が悪く、脳が過剰に反応してしまう
このような背景から、ちょっとした刺激でも「くすぐったさ爆発」になるのです。
また、ODの人がくすぐったさを強く感じやすい部位にも共通点があります。
くすぐったさ地帯トップ3
① 足裏・膝裏
足裏は感覚神経の密集地帯。しかも起立性調節障害では血流が悪く、神経が酸欠になっていることも。
その結果、くすぐったさのセンサーがビンビンに反応してしまいます。
② 脇腹・背中
ここは交感神経が働きやすく、筋膜も硬くなりやすい部位。
姿勢の乱れやストレスが加わると、触られた瞬間に「わっ!」と体が跳ね返ります。
③ 首・肩周辺
自律神経の切り替えポイントとも言える首〜肩まわり。疲労や緊張が溜まっていると、優しく触れただけでも「うひゃっ」となってしまうのです。
エネルギー浪費を防ぐ!くすぐったさ改善対策5選
「どうせ私は一生くすぐったい体質…」と諦めるのはまだ早い!
ここからは、体力をムダに消耗しないためのくすぐったさ対策を5つ紹介します。
① 足湯&温活で血流アップ!
くすぐったさが強い人は、血流が悪いことが多いです。
毎日10〜15分の足湯を習慣にするだけで、末端の血流が改善され、神経の過敏性が緩和されます。
おすすめ:
・天然塩を入れる(ミネラル補給にも◎)
・就寝前に行うと入眠もスムーズ
② 深呼吸で自律神経リセット
起立性調節障害は呼吸が浅くなりがち。
深呼吸(特に腹式呼吸)を行うことで、副交感神経が優位になり、神経のピリピリ感が落ち着いてきます。
1日3回、1分ずつでもOK!
呼吸が整うと、くすぐったさの感じ方も変わってきますよ。
③ 筋膜リリースで敏感ゾーンを鎮める
背中や腰、首の筋膜が硬くなるとくすぐったさが増します。
フォームローラーやストレッチポールを使って、1日5分の筋膜リリースを習慣に!
特におすすめ:
・背中〜脇腹に沿ってゴロゴロ
・太ももの裏〜ふくらはぎをゆっくりほぐす
④ マグネシウム&ビタミンB群を摂ろう
神経の過敏性には栄養も大きく関係しています。
特におすすめなのは、マグネシウムとビタミンB群。
-
マグネシウム:神経の興奮を鎮めるミネラル(海藻、ナッツ、塩に含まれる)
-
ビタミンB群:神経伝達を円滑にするビタミン(玄米、卵、納豆に多い)
⑤ 「くすぐったくないタッチ」を身につける
マッサージを受けるときや親子のスキンシップでは、**「撫でる」のではなく、「圧をかけて静止する」**タッチが有効。
くすぐったくない触り方を工夫するだけでも、リラックス度が全然違います。
まとめ:くすぐったさは“見えないエネルギードレイン”だった!
起立性調節障害の人にとって、「くすぐったさ」は決して笑い話ではなく、体力を削る真剣な問題です。
ちょっと触れただけで全力で戦闘モードに入ってしまう…そんな体にエネルギーを残してあげるには、「くすぐったさ=自律神経の乱れサイン」と受け止め、日々のケアを続けることが大切です。
笑ってごまかすのはもう卒業!
自分の体を正しく理解して、「くすぐったさ貧乏」から抜け出していきましょう!